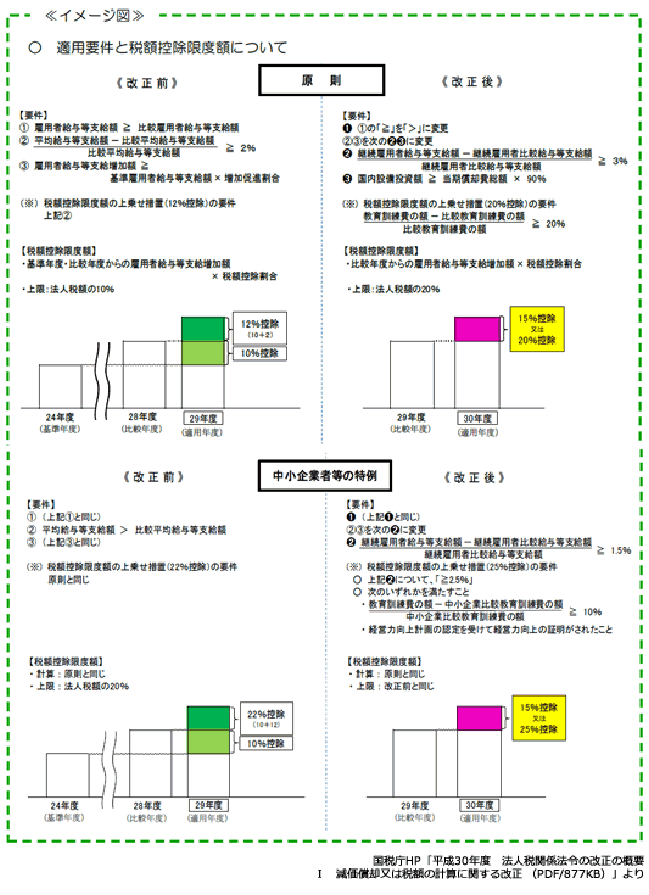年度別税制改正項目
2010/04/02平成22年度 重要改正-グループ税制等-
立川市 税理士事務所平成22年度の税制改正が22.3.24成立しました。法人税に関する主なものとしては
1 100%グループ内の法人間の譲渡取引の損益の繰延
100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益の計上を繰り延べる等、資本に関係する取引等に係る整備が行われました。
(H22.10.1以後の譲渡について適用)
2 清算所得課税の廃止及びこれに伴う措置が講じられました。
清算所得課税を廃止するとともに、清算中の内国法人である普通法人(または協同組合等)に各事業年度の所得に対する法人税が課されることとなりました。
(従来は清算所得課税つまり残余財産がある場合に課税されていました。)
また、法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、青色欠損金額等以外の欠損金額を損金の額に算入することとされました。
(H22.10.1以後の解散が行われる場合について適用)
3 いわゆる「1人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員
給与の損金不算入制度)が廃止されました。給与所得控除の「二重控除」の問題については解消するための抜本的措置を平成23年度改正で講じることとされました。
(H22.4.1前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例によることとされています。)
1 100%グループ内の法人間の譲渡取引の損益の繰延
100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益の計上を繰り延べる等、資本に関係する取引等に係る整備が行われました。
(H22.10.1以後の譲渡について適用)
2 清算所得課税の廃止及びこれに伴う措置が講じられました。
清算所得課税を廃止するとともに、清算中の内国法人である普通法人(または協同組合等)に各事業年度の所得に対する法人税が課されることとなりました。
(従来は清算所得課税つまり残余財産がある場合に課税されていました。)
また、法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、青色欠損金額等以外の欠損金額を損金の額に算入することとされました。
(H22.10.1以後の解散が行われる場合について適用)
3 いわゆる「1人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員
給与の損金不算入制度)が廃止されました。給与所得控除の「二重控除」の問題については解消するための抜本的措置を平成23年度改正で講じることとされました。
(H22.4.1前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例によることとされています。)
2010/07/09平成22年度改正 ―消費税―
H22年4月1日以後に次の①、②のいずれにも該当する事業者は、免税事業者となることや簡易課税制度を適用して申告することが一定期間(3年間)制限されることになりました。
①「課税事業者選択届出書」を提出し、同日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合又は資本金1千万円以上の法人を設立した場合で
②課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中又は新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、
○免税事業者となることはできません(法9⑦、法12の2②)
○また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。(法37②)
*つまり、一般課税による申告が強制されます。
①「課税事業者選択届出書」を提出し、同日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合又は資本金1千万円以上の法人を設立した場合で
②課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中又は新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、
○免税事業者となることはできません(法9⑦、法12の2②)
○また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。(法37②)
*つまり、一般課税による申告が強制されます。
- 調整対象固定資産
- 棚卸資産以外の資産で、建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具器具備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で税抜き価額で100万円以上のものが該当します。(法2①十六、令5)
立川市 税理士事務所なお、この改正は個人事業者が法人成りした際に、設立した法人が調整対象固定資産を引き継ぐ場合にも適用されることになるので注意が必要です。
2010/09/02平成22年度グループ法人税制の概要
立川市 税理士事務所グループ法人税制(22.10.1以降開始事業年度又は取引から適用分)
|
区分
|
主な改正内容
|
100%グループ法人間取引
(個人・法人による「一の者」による完全支配) |
|
|
譲渡法人(又は寄付側)
|
譲受法人(又は受取側)
|
||
|
資産の譲渡
(法61の13①) |
譲渡損益調整資産
(帳簿価額1,000万円以上) ①固定資産 ②棚卸土地 ③有価証券(売買目的除 く) ④金銭債権 ⑤繰延資産 (改正内容) * 譲渡損益調整資産の譲渡 損益を繰延べる(一回のみ) (譲渡・譲受法人双方の通知 制度がある) * 譲受法人が他に転売した時等は、繰延べられた譲渡損益を計上する * 完全支配関係が消滅した時には、繰延べられた譲渡損益を計上する * 譲受法人が減価償却した時は、下記(注1)により益金算入の調整が必要になる * 消費税は譲渡価額で課税 |
①会計上は譲渡損益を計上する
②税務上は * 譲渡益は別表四で減額調整額として減算(留保) * 譲渡損は増額調整額として加算(留保)欄へ記入する * 五表は譲渡損益調整資産の△譲渡利益(譲渡損失)金額としてそれぞれ増欄に記入する (完全支配関係のある内国法人 間取引のみ) |
会計・税務とも通常通り、減価償却も通常通り実施する
|
|
個人・外国法人間は適用なし
|
(完全支配関係のある内国法人間取引のみ)
|
(完全支配関係のある内国法人間取引のみ)
|
|
区分
|
主な改正内容
|
100%グループ法人間取引
(個人・法人による「一の者」による完全支配) |
|
|
譲渡法人(又は寄付側)
|
譲受法人(又は受取側)
|
||
|
資産の譲渡
(法61の13①) |
(個人による完全支配)
・寄付側は一定限度超分が損金不算入となる ・受入側は全額益金算入 (時価により損益を認識) (法人による完全支配) ・寄付法人は全額損金 不算入 ・受入法人は全額益金 不算入 (時価により損益を認識) * 株式保有法人の株式の税務上の帳簿価額修正が必要になる (仕訳) 子会社株式/利益積立金 又は 利益積立金/子会社株式 (算式) 帳簿価額の修正金額= 受増益の額×持分割合- 寄付金の額×持分割合 |
(土地の贈与の場合)
① 会計上 寄付金/土地 ②税務上 別表四で寄付金の損金不算入として加算(流出) |
① 会計上
土地/受増益 ②税務上 別表四⑱で受増益の益金 不算入として減算(*流出) |
|
(注2)役務提供の場合の問題
|
(法人による完全支配関係に限る)
|
(法人による完全支配関係に限る)
|
|
区分
|
主な改正内容
|
100%グループ法人間取引
(個人・法人による「一の者」による完全支配) |
|
|
譲渡法人(又は寄付側)
|
譲受法人(又は受取側)
|
||
|
受取配当金
(法23①④) |
(益金不算入の計算の際の
株式の区分) ①完全子法人株式等 ②関係法人株式等 (25%以上保有かつ配当の 効力の生ずる以前6月以上保 有 株式) ③上記以外の内国法人株式 (完全子法人株式についての受取配当) →負債利子を控除せず、全額が益金不算入 ①は全額益金不算入 ②は負債利子控除した残額が益金不算入 ③については負債利子控除した残額の50%が益金 不算入 |
(仕訳)
未払配当金/現金 預り源泉税 |
(仕訳)
現金/受取配当金 別表四において全額を減算 (*流出) |
|
(注2)役務提供の場合の問題
|
(法人による完全支配関係に限る)
|
(法人による完全支配関係に限る)
|
|
区分
|
主な改正内容
|
100%グループ法人間取引
(個人・法人による「一の者」による完全支配) |
|
|
譲渡法人(又は寄付側)
|
譲受法人(又は受取側)
|
||
|
株式の譲渡損益と
みなし配当 (法61の2⑯) |
(従来)
株式の発行法人Sが親法 人等 Pから自己株式を取得すると譲渡法人Pはみなし配当と譲渡損益の両方が発生する (改正内容) 譲渡法人Pについてみなし配当 は発生するが、譲渡損益は発生させず、資本金等の額として処理する (みなし配当の計算式) みなし配当=交付金銭-(A) (A)=資本金等の額× 取得する自己株式数/発行済株式数 |
Pは受取(みなし)配当は計上
するが譲渡損益は資本金等の 額として処理する (Pの仕訳例) ①売却損の場合 現金預金/有価証券 資本金等/受取(みなし)配当 ②売却益の場合 現金預金/有価証券 受取(みなし)配当 資本金等 |
(Sの仕訳例)
資本金等/現金預金 利益積立金 (みなし配当) |
|
区分
|
主な改正内容
|
100%グループ法人間取引
(個人・法人による「一の者」による完全支配) |
|
|
譲渡法人(又は寄付側)
|
譲受法人(又は受取側)
|
||
|
完全支配子法人の
解散と残余財産の分配 (法61の2⑯) |
(通常は)
①みなし配当と ②株式の譲渡損益が発生する (改正内容) 完全支配子会社の解散に伴い 残余財産の分配を受けた場合には、受取配当は発生するが,譲渡損益 (株式の売却益又は消耗損)は発生させず資本金等の額とする (算式) みなし配当=残余財産の分配の金額-資本金等の金額 |
(株式保有法人)
○売却損(消却損)の場合 現金預金/有価証券 資本金等/受取(みなし)配当 |
(Sの仕訳例)
資本金等/現金預金 利益積立金 (みなし配当) |
|
区分
|
主な改正内容
|
100%グループ法人間取引
(個人・法人による「一の者」による完全支配) |
|
|
譲渡法人(又は寄付側)
|
譲受法人(又は受取側)
|
||
|
適確現物分配
(法62の5③) |
(現物分配とは)
株主に対して次のような事由により金銭以外の資産を交付すること ・剰余金の配当 ・解散による残余財産の分配 ・自己株式の取得 (通常の現物分配) ①分配した法人 分配資産の効力発生時の時価と帳簿価額の差額で譲渡損益を認識する ②分配を受けた法人 分配を受けた資産の時価をベースに配当を認識する (適格現物分配の場合) 現物分配を行う法人の株主が現物分配の直前において分配会社と 完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等)のみであるもの ①分配した法人 分配資産の効力発生時の帳簿価額により譲渡したものとする (譲渡損益を認識せず、源泉徴収もしない) ②分配を受けた法人 分配法人から資産とそれに相当する利益積立金額を、 分配直前の帳簿価額で引継ぐ(資産の移転により生ずる収益は益金の額に算入しない) |
剰余金の配当を金銭以外の資産で行った場合の税務処理)
利益積立金/有価証券 (帳簿価額による) (残余財産の分配を金銭以外の資産で行った場合の税務処理) 資本金等/土地 利益積立金額 (みなし配当) * 残余財産の分配として交付した資産の帳簿価額から資本金等の金額を控除した金額は、配当金とみなす(源泉徴収はしない) |
(剰余金の分配を受けた法人)
有価証券/利益積立金(現物分配法人の帳簿価額による) (解散により分配を受けた法人) 土地/利益積立金 有価証券 *土地の取得価額は分配法人の帳簿価額を引継ぐ *みなし配当の額は交付を受けた土地の帳簿価額から 分配法人の資本 金等の額を控除した金額であるが配当(収益)として認識せず利益積立金として引継ぐ * 分配をうけた有価証券については譲渡損益を計上する 譲渡収入= 交付を受けた土地の帳簿価額-みなし配当の金額 |
(注1)減価償却の場合の譲渡法人の繰延譲渡損益額の調整(戻入)
(原則) 繰延譲渡損益額×譲渡法人において償却費として損金に算入された金額/譲 受法人の取得価額
(簡便法)繰延譲渡損益額×譲渡法人の事業年度の月数/譲受法人が摘要する耐用年数×12
(譲渡の日の前日までの期間を除く)
(注2)完全支配関係法人の役務提供の場合の問題(無利息貸付の場合)
(貸付法人側の仕訳)(借入法人側仕訳)
寄付金/受取利息 支払利息/受贈益
寄付金は損金不算入、受贈益は益金不算入で支払利息については減額更正(更正の請求)か?
*なお、適用に当たっては念のため、それぞれの条文の再確認をお願います。
(原則) 繰延譲渡損益額×譲渡法人において償却費として損金に算入された金額/譲 受法人の取得価額
(簡便法)繰延譲渡損益額×譲渡法人の事業年度の月数/譲受法人が摘要する耐用年数×12
(譲渡の日の前日までの期間を除く)
(注2)完全支配関係法人の役務提供の場合の問題(無利息貸付の場合)
(貸付法人側の仕訳)(借入法人側仕訳)
寄付金/受取利息 支払利息/受贈益
寄付金は損金不算入、受贈益は益金不算入で支払利息については減額更正(更正の請求)か?
*なお、適用に当たっては念のため、それぞれの条文の再確認をお願います。
2013/09/29平成22年度 重要改正-清算所得課税の廃止-
平成22年度の税制改正では、精算法人に対する清算所得課税が廃止され、継続企業の通常事業年度の所得課税が行われるようになりました。(H22.10.1以後の解散から適用)
従来通り適用されるものと、新たに創設、改正等されたものがあり適用を誤ると大変なので主なものを整理すると以下のようになります。
従来通り適用されるものと、新たに創設、改正等されたものがあり適用を誤ると大変なので主なものを整理すると以下のようになります。
|
区分
|
内容
|
条文
|
|
従来通り
適用されるもの |
解散した場合のみなし事業年度
|
法法14一、二、二十一、二十二
|
|
解散による残余財産の分配によるみなし配当
|
法法24①三
|
|
|
精算中の圧縮記帳の不適用
|
法法42、措法64等
|
|
|
精算中の特定同族会社の留保金課税の不適用
|
法法67①
|
|
|
精算中の中間申告の不適用
|
法法71①
|
|
|
解散した場合の青色欠損金の繰戻し還付の特例
|
法法80④、措法66の13
|
|
|
精算中の特別償却および特別税額控除の不適用
|
措法42の4、42の5等
|
|
|
精算中の準備金の積立ての不適用
|
措法55、55の2等
|
|
区分
|
内容
|
条文
|
|
新たに創設、
改正されたもの |
残余財産の分配又は引渡しは資本等取引に該当すること
|
法法22⑤
|
|
残余財産が確定した場合には一括償却資産の金額は損金算入すること
|
法令133の2④
|
|
|
残余財産の確定事業年度においては原則として貸倒引当金および返品調整引当金は設定できないこと
|
法法52、53
|
|
|
完全支配関係がある子会社が解散し、その残余財産が確定した場合には原則として子会社の控除未済欠損金額は親会社に引継ぐこと
|
法法57②、58②
|
|
|
解散し残余財産がないと見込まれる場合(解散時に実質的に債務超過である場合)には、控除期限切れの欠損金額の控除ができること
|
法法59③
|
|
|
完全支配関係がある子会社が解散し、その子会社株式を有しなくなった場合には、子会社株式の帳簿価額は帳簿価額相当とされ、譲渡損益の計上はできないこと
|
法法61の2⑯
|
|
|
解散し残余財産の全部の分配または引渡しにより資産の移転をする場合、的確現物分配を除き、残余財産確定時の時価により譲渡したものとして課税所得を計算すること
|
法法62の5①~③
|
|
|
残余財産確定事業年度の事業税額は、その事業年度に損金算入すること
|
法法62の5⑤
|
|
|
精算中の法人であっても、法人税率は、各事業年度の所得に対する税率であること
|
法法66
|
|
|
精算中の各事業年度は通常の事業年度と同様に、原則として事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内に確定申告すること(残余財産が確定した場合には1ケ月以内)
|
法法74
|
|
|
精算中に終了する事業年ぢにおいては、資本金の額に関係なく青色欠損金の繰戻し還付請求ができること
|
総総80、措法66の⑬
|
|
|
粉飾決算による過大納付法人税について残余財産が確定した場合、合併による解散をした場合、破産手続開始の決定によるかいさんをした場合には即時還付を受けられること
|
法法134の2
|
|
|
精算中の各事業年度にあっても、交際費等の損金不算入が適用されること
|
措法61の4
|
(注)一部省略しています。
2011/12/30復興特別税(復興特別税ー23.11.30成立分―)
東日本大震災の復興財源措置として平成23年11月30日成立した復興特別所得税及び復興特別法人税の概容については
1 復興特別所得税
その年分の基準所得税額に2.1/100の税率を乗じて計算した金額とすることとされました。そして課税の対象は
(1)居住者又は非居住者に対して課される平成25年から平成49年までの各年分の所得税に係る基準所得税額を課税の対象とすることとされました。
(2)内国法人又は外国法人に対して課される平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得に対する所得税にかかる基準所得税額を課税の対象とすることとされました。
*基準所得税額とは定義では5項目ありますが一部を記載省略します
イ 非永住者以外の居住者すべての所得に対する所得税額
ロ 非居住者については国内源泉所得に対する所得税の額
ハ 内国法人については利子等及び配当等に対する所得税額
とされています。
*従って、平成25年1月1日以降使用する源泉徴収税額表は国税庁HP等で確認する必要があります。
(1)居住者又は非居住者に対して課される平成25年から平成49年までの各年分の所得税に係る基準所得税額を課税の対象とすることとされました。
(2)内国法人又は外国法人に対して課される平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得に対する所得税にかかる基準所得税額を課税の対象とすることとされました。
*基準所得税額とは定義では5項目ありますが一部を記載省略します
イ 非永住者以外の居住者すべての所得に対する所得税額
ロ 非居住者については国内源泉所得に対する所得税の額
ハ 内国法人については利子等及び配当等に対する所得税額
とされています。
*従って、平成25年1月1日以降使用する源泉徴収税額表は国税庁HP等で確認する必要があります。
2 復興特別法人税
平成24年4月1日から平成27年3月31日の間(指定期間)の法人の各課税事業年度の基準法人税額(課税標準法人税額)を課税の対象とすることとされました。
税額の計算は基準法人税額×10/100とされました。
*法人が各事業年度において課された復興特別所得税の額は、当該事業年度の復興特別法人税の額から控除することとされました。
税額の計算は基準法人税額×10/100とされました。
*法人が各事業年度において課された復興特別所得税の額は、当該事業年度の復興特別法人税の額から控除することとされました。
(サービス提供地域)
小林仁志税理士事務所 立川市 昭島市 国分寺市 国立市 東大和
市 武蔵村山市 八王子市 福生市 あきるの市 羽村町 府中市 調布市 狛江市 町田市
日野市 多摩市 稲城市 東村山市 小平市 東京都区内
小林仁志税理士事務所 立川市 昭島市 国分寺市 国立市 東大和
市 武蔵村山市 八王子市 福生市 あきるの市 羽村町 府中市 調布市 狛江市 町田市
日野市 多摩市 稲城市 東村山市 小平市 東京都区内
2011/06/28平成23年度 重要改正-消費税-6.22成立分
1 免税事業者の要件が以下のように見直しになりました(個人・法人)。
(1)上半期で課税売上高が1,000万円を超える場合
次に掲げる事業者の特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、その事業者については、事業者免税点制度は適用されません。
次に掲げる事業者の特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、その事業者については、事業者免税点制度は適用されません。
|
区分
|
特定期間とは
|
|
|
個人
|
その前年の1月1日~6月30日までの期間
|
|
|
法人
|
前事業年度が
7ヵ月超の場合 |
その事業年度の前事業年度開始の日から6ヵ月間
|
|
前事業年度が7ヵ月
以下の場合 |
その事業年度の前々事業年度開始の日から6ヵ月間
(前々事業年度から5ヵ月以下の場合には、その期間) |
|
(2)給与支払金額による判定
上記(1)の判定に当たっては、上記(1)の事業者は(1)の課税売上高の金額に代えて特定期間に支払った給与等の支払額の合計をもって、課税売上高とすることができます。
つまり、前々事業年度の課税売上金額と上記課税売上金額との2段階で判定することになります。
*平成25年1月1日以後に開始する事業年度(個人は25年分)から適用されます。
上記(1)の判定に当たっては、上記(1)の事業者は(1)の課税売上高の金額に代えて特定期間に支払った給与等の支払額の合計をもって、課税売上高とすることができます。
つまり、前々事業年度の課税売上金額と上記課税売上金額との2段階で判定することになります。
*平成25年1月1日以後に開始する事業年度(個人は25年分)から適用されます。
2 95%ルールが見直されました。
課税売上高が95%以上の場合に、課税仕入れ等の税額の全額を仕入控除できる制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算します。)を超える事業者には適用されないこととされないこととなりました。
*平成24年4月1日以後開始する課税期間(個人は25年分)から適用されます。
*平成24年4月1日以後開始する課税期間(個人は25年分)から適用されます。
3 その他
消費税還付申告書(仕入控除の控除不足額の記載のあるものに限ります)を提出する事業者に対し任意提出している「仕入控除に関する明細書」が添付が義務付けられました。(平成24年4月1日以後提出する還付申告書について適用)
2012/03/31平成24年度源泉所得税納期の特例(改正)
「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20 日とされました。この改正は、平成24 年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用されます。
1 制度の概要
給与等の支給人員が常時10 人未満である源泉徴収義務者は、「納期の特例」の承認を受けることで給与等や退職手当等、一定の報酬等(以下「給与等及び退職手当等」といいます。)から徴収した源泉所得税を年2回(7月10 日、翌年1月10 日)にまとめて納付することができます。
また、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税については、届出書を提出し一定の要件を満たすことで納期限を翌年1月20 日とする「納期限の特例」の制度が設けられています。
また、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税については、届出書を提出し一定の要件を満たすことで納期限を翌年1月20 日とする「納期限の特例」の制度が設けられています。
2 改正の内容
「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20 日とされました。これに伴い、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度は廃止されました。
(サービス提供地域)
小林仁志税理士事務所 立川市 昭島市 国分寺市 国立市 東大和
市 武蔵村山市 八王子市 福生市 あきるの市 羽村町 府中市 調布市 狛江市 町田市
日野市 多摩市 稲城市 東村山市 小平市 東京都区内
小林仁志税理士事務所 立川市 昭島市 国分寺市 国立市 東大和
市 武蔵村山市 八王子市 福生市 あきるの市 羽村町 府中市 調布市 狛江市 町田市
日野市 多摩市 稲城市 東村山市 小平市 東京都区内
2012/04/26復興特別所得税(所得税額控除)
法人の受け取る預貯金の利子や配当には、H25.1.1から復興特別所得税(2.1%)が課税されています。そして、その税額は復興特別法人税額から控除できることとされています(復財確法49⑤)。しかし、利子等の支払調書には所得税額と復興特別所得税額は合計で表示されるため(復得所法省令7)、支払調書の税額を基に所得税額と復興特別所得税額に配分(区分)計算する必要が出てきます。
1 配分処理の方法(復財確法28⑥)
給与等の支給人員が常時10 人未満である源泉徴収義務者は、「納期の特例」の承認を受けることで給与等や退職手当等、一定の報酬等(以下「給与等及び退職手当等」といいます。)から徴収した源泉所得税を年2回(7月10 日、翌年1月10 日)にまとめて納付することができます。
また、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税については、届出書を提出し一定の要件を満たすことで納期限を翌年1月20 日とする「納期限の特例」の制度が設けられています。
また、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税については、届出書を提出し一定の要件を満たすことで納期限を翌年1月20 日とする「納期限の特例」の制度が設けられています。
-
①「復興特別所得税額」=源泉徴収税額×2.1/102.1
-
②「所得税額」=源泉徴収税額-①「復興特別所得税額」
2 端数処理(復得所令4,10)
①の計算の際生じた1円未満の端数については、50銭超の場合は切上、50銭以下の場合は切捨てます。
*端数処理は原則は支払を受ける都度となっていますが以下の表のように、合理的な方法であれば簡易な計算の配分処理も認めることとされています。
*端数処理は原則は支払を受ける都度となっていますが以下の表のように、合理的な方法であれば簡易な計算の配分処理も認めることとされています。
|
別表六(一)
|
原則
|
簡便計算の例
|
|
①預貯金のりし及び合同運用信託の収益の分配
|
支払を受ける都度
|
期末一括処理
|
|
②公社債の利子等
|
銘柄ごと期末一括処理(所有期間
按分の計算の簡便方法の場合) |
|
|
③剰余金・利益の配当及び剰余金の分配
|
||
|
④集団投資信託の収益の分配
|
||
|
⑤その他
|
3 では、普通預金の利息の場合はどのように計算するのでしょうか?
今までですと、所得税が15%、住民税が5%の合計20%が課税されていました。そして、1-20%=0.8で手取り額を割返して支払額を計算していました。
これがH25.1.1以降は
これがH25.1.1以降は
-
①所得税 15 %
-
②復興特別所得税 0.315%(15%×0.021)
-
③住民税 5 %
の合計20.315%が課税されていることになります。従って、1-20.315%=0.79685で割返せば支払額(税込)が計算できることになります。
普通預金利息振込金額年間合計500円の例ですと
普通預金利息振込金額年間合計500円の例ですと
- 手取り金額
- 500円
- 利子の総額
- 500円÷0.79685=627円(1円未満切捨)
- 所得税+復興特別所得税
- 627円×0.15315(①+②)=96円(1円未満切捨)
- 復興特別所得税
- 96円×0.315/15.315=2円(50銭以下切捨、50銭超切上)
- 所得税
- 96円-2円=94円
- 住民税
- 627円×0.05=31円 (1円未満切捨)
となりました。
2013/11/28平成25年度 税制改正(交際費、税額控除、所得税率)
1 交際費課税の改正
資本金1億円以下の中小法人に対する定額控除限度額が600万円から800万円までにひき上げられました。また、従来 定額控除限度内であっても10%の損金不算入措置が廃止されることになりました。
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度から適用となります。
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度から適用となります。
- 国内雇用者
- 法人の使用人のうち、法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として労働基準法に規定する賃金台帳に記載された者をいいます。役員とその特殊関係者および使用人兼務役員は除かれます。
- 一定要件
- 適用年度において以下の要件を全て満たす必要があります。
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること
用者給与等支給額とは
適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対す
る給与等の支給額をいいますが、その給与の支給に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額とされ、
例えば
(1)労働者の雇入れ人数に応じて国等から支給を受けた助成金の金額
(2)受け入れた給与負担金の額
等は控除する必要があります。(措通42の12の4-2)
基準雇用者給与等支給額とは、
平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の開始の日の前日を含む事業年度の(以下「基準事業年度」といいます。)損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
比較雇用者給与等支給額とは、
適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
平均給与等支給額とは
以下の算式により計算した金額をいいます。
平均給与等支給額=(雇用者給与等支給額-日雇い労働者に対する給与等支給額)÷適用年度における給与等月別支給対象者の数の合計額
給与等月別支給対象者とは
適用年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者をいいます。
(損金算入のもの、日雇い労働者を除きます)
比較平均給与等支給額とは、
以下の算式により計算した金額をいいます。
(注)・基準雇用者給与等支給額の算定において、基準事業年度と適用事業年度の月数が異なる場合、新たに設立された法人である場合等の調整計算の詳細は法文をお読みください。
・「雇用者の数が増加した場合の法人税の特別控除」(措法42条の12)の適用を受ける場合にはこの制度の適用を受けられませんので注意が必用です。
・国税庁パンフレット参照
適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対す
る給与等の支給額をいいますが、その給与の支給に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額とされ、
例えば
(1)労働者の雇入れ人数に応じて国等から支給を受けた助成金の金額
(2)受け入れた給与負担金の額
等は控除する必要があります。(措通42の12の4-2)
基準雇用者給与等支給額とは、
平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の開始の日の前日を含む事業年度の(以下「基準事業年度」といいます。)損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
比較雇用者給与等支給額とは、
適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
平均給与等支給額とは
以下の算式により計算した金額をいいます。
平均給与等支給額=(雇用者給与等支給額-日雇い労働者に対する給与等支給額)÷適用年度における給与等月別支給対象者の数の合計額
給与等月別支給対象者とは
適用年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者をいいます。
(損金算入のもの、日雇い労働者を除きます)
比較平均給与等支給額とは、
以下の算式により計算した金額をいいます。
(注)・基準雇用者給与等支給額の算定において、基準事業年度と適用事業年度の月数が異なる場合、新たに設立された法人である場合等の調整計算の詳細は法文をお読みください。
・「雇用者の数が増加した場合の法人税の特別控除」(措法42条の12)の適用を受ける場合にはこの制度の適用を受けられませんので注意が必用です。
・国税庁パンフレット参照
2 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(創設)
課税所得4000万円超について45%の税率を設けることとされました。(従来は1800万円超が40%とされていました。)
平成27年分以後の所得税について適用されます。
平成27年分以後の所得税について適用されます。
2014/04/16平成25年度 税制改正(印紙税)
平成25年度税制改正では「印紙税」について主に2点の改正が行われています。
1 金銭又は有価証券の受取書の免税点の引上げについて
事業者の納税事務の簡素化を図る観点や低額な文書の作成割合が高いという受取書の作成実態等を踏まえ、免税店の水準を3万円未満から5万円未満に引き上げられました。
2 不動産の譲渡に関する契約書等に係る税率の特例措置の適用期限の延長
平成25年3月31日までの間に作成される「不動産譲渡契約書等」のうち、契約金額が1千万円を超えるものについては、その印紙税額を25%から10%に軽減することとされていたところ、改正では、住宅・土地取引の現状や消費税率の段階的な引き上げが予定されていることなどを踏まえ、この特例措置の適用期限を5年延長するとともに、軽減割合と対象範囲を拡充させています。
以上の改正は平成26年4月1日以後に作成される文書に対して適用されるため印紙の貼り間違いの無いよう気をつけて下さい。
以上の改正は平成26年4月1日以後に作成される文書に対して適用されるため印紙の貼り間違いの無いよう気をつけて下さい。
2014/04/02平成26年度 税制改正(交際費課税等)
平成26年度税制改正が3月20日成立しています。
主な内容としては
主な内容としては
1 所得課税関係
給与所得控除の上限額が適用される給与収入 現行1500万円(控除額245万円)を平成28年分から1200万円(控除額230万円)に平成29年分から1000万円( 〃 220万円)に、それぞれ引き下げられます。
この給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得の源泉徴収税額表等の見直しが行われることになっています。
この給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得の源泉徴収税額表等の見直しが行われることになっています。
2 法人課税関係
-
○賃金上昇を促すため、基準年度と比較して「雇用者給与等支給額」の増加割合を緩和した「所得拡大促進税制」については要件の見直しと適用期限の2年延長が行われました。
-
○平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、「接待飲食費」の額の100分の50相当額を超える部分の金額を損金の額に算入せず、「接待飲食費」の額の50%相当額まで損金算入できることとされました。
なお、中小法人に係る損金算入の特例については、現行800万円の定額控除か上記50%損金算入かの選択適用ができることとされています。 -
○復興特別法人税における課税事業年度等の判定の基礎となる指定期間を平成24年4月1日から26年3月31日までとし、1年前倒しで廃止することとされました。
また、法人が各事業年度(課税事業年度を除く)に利子及び配当等に課される復興特別所得税額は各事業年度の所得税額とみなし、法人税額から控除等(平成26年4月1日以後開始事業年度から適用)する規定の整備が行われました。
2014/07/24平成26年度 重要改正(簡易課税みなし仕入率の改正)
○消費税 簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われました。
現在、第4種事業(みなし仕入率60%)に該当している「金融業及び保険業」を第5種事業(みなし仕入率50%)に、第5種事業(みなし仕入率50%)に該当している「不動産業」を新たに設ける第6種事業(みなし仕入率40%)とし、それぞれのみなし仕入率を10%引き下げることとされました。
この改正は原則として平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用します。 ただし、平成26年10月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出している事業者であって、平成27年4月1日以後に開始する課税期間が簡易課税制度の強制適用(2年間簡易課税を継続)を受ける課税期間である場合(消法37⑤)には、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する課税期間の末日以後に開始する課税期間から適用することとされています(改正消令不足1二、4)。
つまり、経過措置により改正前の事業区分と税率を2年間適用するには平成26年9月30日までに届出を出しておく必要があると言うことです。
現在、第4種事業(みなし仕入率60%)に該当している「金融業及び保険業」を第5種事業(みなし仕入率50%)に、第5種事業(みなし仕入率50%)に該当している「不動産業」を新たに設ける第6種事業(みなし仕入率40%)とし、それぞれのみなし仕入率を10%引き下げることとされました。
この改正は原則として平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用します。 ただし、平成26年10月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出している事業者であって、平成27年4月1日以後に開始する課税期間が簡易課税制度の強制適用(2年間簡易課税を継続)を受ける課税期間である場合(消法37⑤)には、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する課税期間の末日以後に開始する課税期間から適用することとされています(改正消令不足1二、4)。
つまり、経過措置により改正前の事業区分と税率を2年間適用するには平成26年9月30日までに届出を出しておく必要があると言うことです。
2014/10/21平成26年度 重要改正(所得拡大促進税制の改正)
平成26年度税制改正において、平成25年度に成立した所得拡大促進税制(措法42条の12の4)の適用要件等が緩和されて適用しやすくなると共に適用期限も2年間延長されました。
この改正は平成26年4月1日以後終了事業年度から適用となります。改正前と改正後を比較すると以下のようになります。
この改正は平成26年4月1日以後終了事業年度から適用となります。改正前と改正後を比較すると以下のようになります。
|
改正前
|
改正後
|
備考
|
|
①当期の「雇用者給与等支給増加額」
/「基準雇用者給与等支給額」≧5% |
①当期の「雇用者給与等支給増加額」/
「基準雇用者給与等支給額」≧2%(注) |
(注)
・平成27年4月1日前に開始する 事業年度 →2%以上 ・平成27年度→3%以上 ・平成28年度→5%以上 |
|
②当期の「雇用者給与等支給額」≧
前期の「雇用者給与等支給額」 |
②当期の「雇用者給与等支給額」≧
前期の「雇用者給与等支給額」 |
|
|
③当期の「平均給与等支給額」≧
前期の「平均給与等支給額」 |
③当期の「平均給与等支給額」>
前期の「平均給与等支給額」 |
改正前は「以上」、改正後は「超える」とされました。
|
|
平均給与等支給額の対象給与等→
日雇い労働者を除く国内雇用者への給与等 |
平均給与等支給額の対象給与等→
継続雇用者への給与等 |
継続雇用者への給与等とは適用年度およびその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者の給与のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいいますが、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等を除きます。
*雇用保険料の納付にかかわらず、高年齢継続被保険者等に該当しない継続雇用者であれば判定の対象とされると解説されています(税務通信3325号 3P)。 |
*26年3月期決算の法人の場合、改正前での判定となりますが、旧要件を満たさなかった場合でも新要件を満たす場合
は、翌27年3月期に26年3月期分の控除額を上乗せできることとされているので(改正附則82)注意が必要となります。
この場合には、平成26年3月期決算で改正前(25年改正)の、この制度を適用していないことが要件となっています。
所得拡大促進税制(創設)の概要については平成25年度税制改正の2を参照してください。
は、翌27年3月期に26年3月期分の控除額を上乗せできることとされているので(改正附則82)注意が必要となります。
この場合には、平成26年3月期決算で改正前(25年改正)の、この制度を適用していないことが要件となっています。
所得拡大促進税制(創設)の概要については平成25年度税制改正の2を参照してください。
2015/05/08平成27年度 税制改正(法人税率等の引下げ)
27年度の主な法人税関係の改正について(抜粋)
1 法人税率等の引下げ(法66、措法42の3の2)
|
区分
|
現行
|
改正
|
|||||
|
27年度
|
28年度
|
||||||
|
年800万円超
|
年800万円以下
|
年800万円超
|
年800万円以下
|
年800万円超
|
年800万円以下
|
||
|
法人税
|
普通法人
(資本金1億円超) |
25.5%
|
23.9%
|
||||
|
普通法人で資本金
1億円以下の法人 |
25.5%
|
15%
|
23.9%
|
15%
|
23.9%
|
15%
|
|
|
事業税
|
法人事業税所得割
*地方特別税を含む *年800万円超所得分の標準税率 |
7.2%
|
6.0%
|
4.8%
|
|||
2 欠損金の繰越控除制度の見直し(法57)
- ①控除限度額
- 現行、課税所得の80%までとされている控除限度額を、27年度から28年度については所得金額の65%まで、29年度以降は50%までとされます。
- ②繰越期間
- 平成29年度以降生じる欠損金について現行9年から10年に延長されます。これに伴い、帳簿書類の保存期間欠損金に係る更正および更正の請求期間も10年に延長されます。
なお、中小企業(資本金1億円以下)については現行のとおり100%控除されます。
また、再建中法人および新設法人の特例の創設についてはここでは省略しています。
平成27年4月1日以後に開始する事業年度において適用されます。
また、再建中法人および新設法人の特例の創設についてはここでは省略しています。
平成27年4月1日以後に開始する事業年度において適用されます。
|
区分
|
現行
|
27年度~28年度
|
29年度以降
|
|
控除限度額
|
所得金額の80%
|
所得金額の65%
|
所得金額の50%
|
|
繰越期間
|
9年
|
10年
|
|
なお、改正の詳細については財務省HPもご確認ください。
2015/08/15平成27年度 社会保障・税番号制度の概要
1 平成25年5月31日公布の「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」によれば、平成27年10月から個人番号・法人番号が通知される予定です。
個人番号・・・市長村長が番号を指定し、「通知カード」により通知します。(保護措置等の対象)
法人番号・・・国税庁長官が指定し書面により通知します。(インターネット等で広く一般に公表)
個人番号は、平成28年1月1日より、申請により「個人番号カード」が交付され、本人確認の際の身分証明書や電子申告等に使える様になっています。
法人番号・・・国税庁長官が指定し書面により通知します。(インターネット等で広く一般に公表)
個人番号は、平成28年1月1日より、申請により「個人番号カード」が交付され、本人確認の際の身分証明書や電子申告等に使える様になっています。
2 個人番号・法人番号は、平成28年1月1日以降、手続きごとに順次利用が開始されます。
税務手続きごとの記載対象は
- 所得税
- 平成28年分から
- 個人消費税
- 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
- 相続税
- 平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
- 贈与税
- 平成28年分から
- 法人税
- 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
- 法人消費税
- 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
- 申請書・届出書
- 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
- 法定調書
- 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
2016/04/22平成28年度 税制改正(法人税率等の引下げ 抜粋)
1 法人税率の引下げ
平成27年度に引き続き、28年度においても税率のさらなる引き下げを行って経済の好循環を後押しする観点から、法人税の税率が次のように改正されました。この改正は平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 なお、一般社団法人等には認可地緑団体、管理組合法人等が含まれます。
|
NO
|
区分
|
現行
|
改正後
|
||
|
28年度~
|
30年度~
|
||||
|
①
|
普通法人(中小法人を除く)
|
23.9%
|
23.4%
|
23.2%
|
|
|
②
|
(a)中小法人
(b)一般社団法人等 (c)人格のない社団 |
年800万円
以下の金額 |
15%
|
15%
|
19%
|
|
年800万円
超の金額 |
23.9%
|
23.4%
|
23.2%
|
||
2 減価償却方法の見直し
今回の改正は、建物と一体的に整備される建物附属設備、建物と同様に長期的に使用される構築物及び鉱業用の建物について、償却方法を定額法に一本化するためのものであり、改正された内容は次のとおりです。平成28年4月1日以後に取得等する資産について適用されます。
|
区分
|
改正前
|
改正後
|
|
建物附属設備
|
定額法又は定率法
|
定額法
|
|
構築物
|
||
|
鉱業用減価償却資産
(建物、建物附属設備及び構築物に限る) |
定額法又は定率法、
生産高比例法 |
定額法又は生産高比例法
|
2017/05/07平成29年度 税制改正(所得税配偶者控除の改正 抜粋)
○平成29年度税制改正では所得税関係のなかで配偶者控除および配偶者特別控除の改正がありました。注意したいのはこの改正は平成30年以後の分であり29年分は従来通りであることです。
所謂103万円の壁と言われる控除対象配偶者の合計所得を現行38万円超76万円未満から38万円超123万円未満に引き上げ、配偶者控除について、次表のとおり控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者について、納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合は所得に応じた段階的な控除額に改正し、いずれも納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は適用できないこととなりました。
所謂103万円の壁と言われる控除対象配偶者の合計所得を現行38万円超76万円未満から38万円超123万円未満に引き上げ、配偶者控除について、次表のとおり控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者について、納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合は所得に応じた段階的な控除額に改正し、いずれも納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は適用できないこととなりました。
|
居住者の合計所得金額
|
控除額
|
|
|
控除対象配偶者
|
老人控除対象配偶者
|
|
|
900万円以下
|
38万円
|
48万円
|
|
900万円超950万円以下
|
26万円
|
32万円
|
|
950万円超1000万円以下
|
13万円
|
16万円
|
|
1000万円超
|
-
|
-
|
○ 改正法案により、従来の控除対象配偶者については「同一生計配偶者」と改められ、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1000万円以下である居住者の配偶者については「控除対象配偶者」と規定されました。
老人控除対象配偶者についても、従来通り控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者としますが、合計所得金額が1000万円以下である配偶者と定められました。
○ 新たに「源泉控除対象配偶者」を規定し、居住者(合計所得金額が900万円以下である者に限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が85万円以下である者と定められました。これらにより、居住者の合計所得金額が900万円以下の源泉控除対象配偶者については月々の源泉徴収の対象となりますが900万円超1000万円以下の居住者に係る控除対象配偶者等については年末調整又は確定申告で適用を受けることになると考えられます。
○ 配偶者特別控除の対象については、配偶者の合計所得金額が現行38万円超76万円未満から38万円超123万円以下に拡充され、従来通り居住者の合計所得金額が1000万円超は適用になりません。
また、配偶者控除と同様に居住者の合計所得金額が①900万円以下②900万円超950万円以下
③950万円超1000万円以下の3区分ごと、配偶者の合計所得金額(9区分)に応じて、それぞれ控除額が逓減されます。
老人控除対象配偶者についても、従来通り控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者としますが、合計所得金額が1000万円以下である配偶者と定められました。
○ 新たに「源泉控除対象配偶者」を規定し、居住者(合計所得金額が900万円以下である者に限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が85万円以下である者と定められました。これらにより、居住者の合計所得金額が900万円以下の源泉控除対象配偶者については月々の源泉徴収の対象となりますが900万円超1000万円以下の居住者に係る控除対象配偶者等については年末調整又は確定申告で適用を受けることになると考えられます。
○ 配偶者特別控除の対象については、配偶者の合計所得金額が現行38万円超76万円未満から38万円超123万円以下に拡充され、従来通り居住者の合計所得金額が1000万円超は適用になりません。
また、配偶者控除と同様に居住者の合計所得金額が①900万円以下②900万円超950万円以下
③950万円超1000万円以下の3区分ごと、配偶者の合計所得金額(9区分)に応じて、それぞれ控除額が逓減されます。
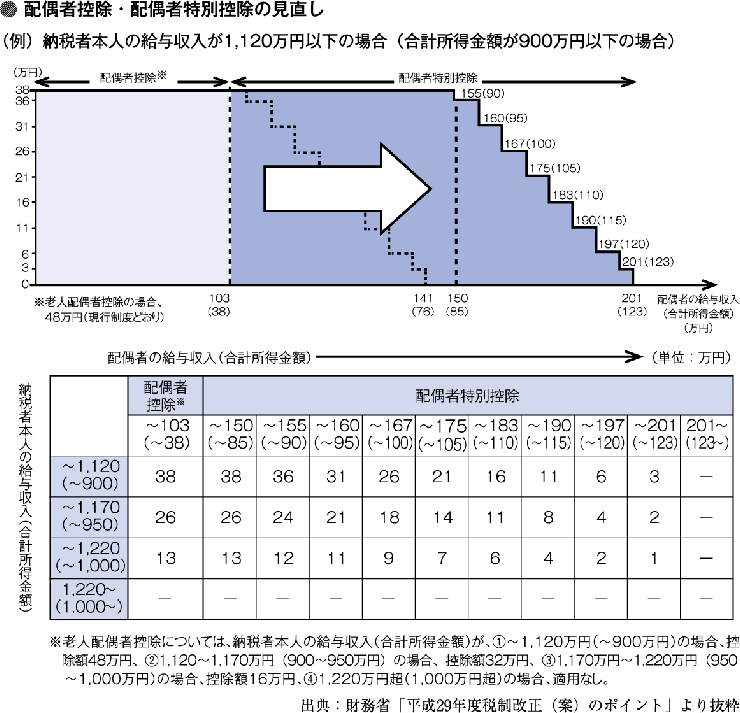
2018/09/12平成30年度 税制改正(雇用者給与関係 抜粋)
中小企業者等の特例の概要
中小企業者等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して、次の(要件)イ及びロを満たすときは、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の15% (次の上乗せ要件ハ及び二を満たす場合には25%)相当額の特別控除ができることとされました。ただし、適用年度の 調整前法人税額の20%相当額が限度とされています。(措法42の12の5②)
要件
イ 雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額
ロ(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)÷継続雇用者比較給与等支給額≧1.5%
ロ(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)÷継続雇用者比較給与等支給額≧1.5%
上乗せ要件
ハ (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)÷継続雇用者比較給与等支給額≧2.5%
二 次のいずれかの要件を満たすこと
(イ)(教育訓練費の額-中小企業比較教育訓練費の額)÷中小企業比較教育訓練費の額≧10%
(ロ)その中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたも ので、その経営力向上計画に従って経営向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたものであること
二 次のいずれかの要件を満たすこと
(イ)(教育訓練費の額-中小企業比較教育訓練費の額)÷中小企業比較教育訓練費の額≧10%
(ロ)その中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたも ので、その経営力向上計画に従って経営向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたものであること